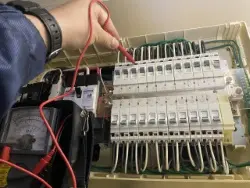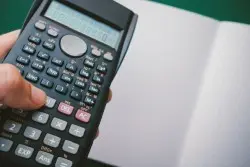水トリー現象
水トリーとは、高圧電線路に用いられるCVケーブルやCVTケーブルの絶縁層で、絶縁劣化がツリー状に成長して絶縁層を貫通し、絶縁破壊を引き起こす現象である。劣化の進展した形状が樹枝状(ツリー状)に見えることからこの名称で呼ばれている。
水が含まれた環境に常時曝されているケーブルで発生することが知られており、ケーブルが長期間浸水されることにより、絶縁劣化が進行してケーブルが劣化し、絶縁破壊へと進行するおそれがある。時間の経過とともに樹枝状に成長し、最終的には絶縁体を貫通して地絡(リーク)や絶縁破壊(ショート)を引き起こす。
CVケーブルは架橋ポリエチレンを用いたケーブルであり、ポリエチレン内部の異物で電界が集中し、ツリー状に劣化が広がっていくことが知られており、ケーブル内部と外部までツリーが接続されると、絶縁破壊となる。高圧ケーブルが地中など水の影響がある場所は、多くが電力会社からの受電ケーブルであり、この部分で電線の事故が発生することで近隣を巻き込んだ停電となる波及事故につながることが多い。
天井裏など水の影響を受けない場所であれば、CVケーブルは20~30年以上継続して使われていることも多く、絶縁抵抗試験や絶縁耐力試験で異常がなければ問題ないとされる。しかし地中埋設となっているケーブルは地中水や雨水、汚泥などにより過酷な環境となっていることが多く、ケーブルの劣化が進行しやすい。

水トリーには、その劣化の進行形状により、外側から進行する「外導水トリー」、内側から進行する「内導水トリー」、ケーブル内部から進行する「ボウタイ状水トリー」があり、外部と内部がつながることで絶縁性能が失われる。
- 外導水トリー:外部半導電層から内側(絶縁体側)へ進行する。外部半導電層が「テープ巻き(E-Tタイプ)」の場合、そのテープの繊維や巻きムラによる突起部(電極不整)が起点となりやすい
- 内導水トリー:導体を包む「内部半導電層」と絶縁体の境界から発生する。製造工程で生じた内部半導電層の微細な突起や、異物の付着による
- ボウタイ状水トリー:絶縁体の内部で発生し、両側へ広がるタイプ。絶縁体(架橋ポリエチレン)の「内部」から発生し、起点を中心に左右(または上下)へ広がる様子が「蝶ネクタイ(ボウタイ)」に似ていることから
高圧のCVケーブルで発生する水トリーを防止するため、ケーブルの内部半導電層と絶縁体、外部半導電層をすべて同時押出する「E-E方式」のケーブルを用いることが推奨されている。電力会社工事や公共工事などではE-E仕様が規定されていることがあるが、ケーブルコストが高くなることもあり、民間工事の多くは外部半導電層をテープ巻き方式とした「E-T方式」のCVケーブルが用いられる。
2023年12月に経済産業省より、「更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起」が発表され、E-Tタイプでの事故が多発していることから、E-Eタイプの高圧CVケーブルを採用する需要家が多くなり、ケーブル確保が困難となっている。
CVケーブルの特徴や仕様についての詳細はCVケーブル・CVTケーブルを参照。