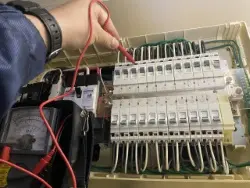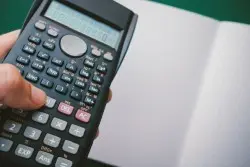需要率とは
需要率は、その系統における需要電力と供給可能な最大電力を比率化したものである。変圧器容量や分電盤の主幹、供給ケーブルサイズを選定する際に使用する要素で、需要率が高いほど、設備の稼働率が高い状態となる。
例えば、100kVAの変圧器に20kVAの空調機が2セット、10kVAの換気ファンが6セット接続されていた場合、全負荷容量を合算すると100kVAとなる。しかし、空調機が朝夕で別々に動くことが決まっていたり、換気ファンが同時運転しないことが決まっていたりという条件があれば、全負荷容量が同時に稼働することはない。この考え方が需要率であり、実際に同時発生する負荷容量と全負荷容量の比率が需要率となる。
通常、100%となるのは「機器が1台のみ」ということになるが、これも「盤単位」「変圧器単位」「建物全体」で考えて需要率を計算することが可能であり、どの点から見ての需要率なのかを把握することが重要である。
電気機器が同時運転しないことを予測・想定して、変圧器や主幹容量、ケーブルサイズを調整できる。同時に運転しないことが明確であるのに、同時に運転することを想定した設備を用意するのは過剰であるという考え方に基づいている。
需要率の設定は、電気設備のイニシャルコストに極めて大きく影響する。需要率を100%で計算した場合と、80%で計算した場合を比較すると、ケーブルサイズ、遮断器容量、変圧器容量などがワンランク以上増減する。
設計対象施設の運用方法を十分理解し、最適な需要率を選定しなければ、過剰設計となる可能性もあり、逆に容量不足の設計ミスとなるおそれもある。工場では、一律な需要率の選定は非常に危険であり、一般的な業務施設の需要率を使うと、配線用遮断器のトリップなどを引き起こす。施設管理者に対して運用方法をヒアリングし、設計基準を補正することが重要である。

各種負荷の需要率の考え方
空調機のインバーター機器では、需要率をできるだけ高く(80%~100%)としなければ、夏場など外気温が高い時期に負荷電流が流れ過ぎてしまい、変圧器のパンクや遮断器の過負荷トリップが発生するおそれがある。需要率を考える場合「最も高い電流値となる瞬間、変圧器・幹線能力の何%で運転するか」を見極める必要がある。
東京近郊の施設で考えると、特殊な工場などを除き、夏場の12:00~14:00頃が電力のピークである。これは空調機の運転がほとんどの電力消費を占めていることによって発生する。
照明の場合、昼光利用によって全点灯していないことが考えられ、変圧器や幹線の需要率を50%程度まで下げられる可能性がある。しかし空調機の場合、需要率はほぼ100%である。場合によってはインバーターへの電源供給が過大になり、定格電流の120%まで電流が流れていることもある。換気ファンや排水ポンプ、エレベーターなどは需要率60~80%で運転しているかと考えられる。
空調機は負荷容量の100%を需要率として幹線計算し、照明やポンプ、換気ファンなどは需要率60%程度で幹線計算をする、というように使い分ければ、経済的な設計が可能である。
最大電力が流れる瞬間を、負荷の性質に合わせて計算することが重要である。これを考えないまま一括で60%といった計算方法をすると、予期せぬ遮断器の動作や停電、電気機器の過熱・発火事故につながる。
契約電力の設定と需要率
契約電力を決める場合、需要率が大きく影響する。高圧受電の場合、1kWあたり約1,600円前後の基本料金を毎月支払う必要があるため、契約電力の設定はランニングコストに大きな影響を及ぼす。
変圧器容量が全て契約電力になることはなく、全変圧器の総容量の40%から50%程度が需要率となるため、合計1,000kVAの変圧器があれば、概ね400kW前後が契約電力となることが多い。(施設用途や、変圧器の設計方法によって大きく変動するので、個別に需要率計算と検討が必要である。)
個々の変圧器に関わる需要率のピーク時間が違うため、全体の需要が集中せず、設備容量の割には契約電力が小さくなる。
動力変圧器に空調機が多く接続されていた場合、ピークは12:00~14:00頃に発生する。動力変圧器への負荷は、ほぼ100%に近い数値が出るであろう。しかし、照明負荷を接続している電灯変圧器は、同じ時間であれば消灯していることから、50%程度しか使用していないことが想像できる。
ピーク時間のずれにより、変圧器が同時に全負荷になることはない。契約電力は比較的小さな数値でも成立する。この「最も高い消費電力が発生する瞬間」の容量を判断し、契約電力とすることで、リーズナブルな契約とできる。
オール電化を除く集合住宅の幹線需要率
集合住宅にあっては、内線規程に一般的な需要率が設定されており、集合住宅の設計に活用できるようになっている。この用地を下回らない範囲で、実情に応じた設計をすることが求められている。
| 戸数 | 需要率 [%] | 最大負荷 [kVA] |
| 1 | 100 | 4.0 |
| 2 | 100 | 8.0 |
| 3 | 100 | 12.0 |
| 4 | 100 | 16.0 |
| 5 | 100 | 20.0 |
| 6 | 91 | 21.8 |
| 7 | 83 | 23.2 |
| 8 | 78 | 25.0 |
| 9 | 73 | 26.3 |
| 10 | 70 | 28.0 |
| 11 | 67 | 29.5 |
| 12 | 64 | 30.7 |
| 13 | 62 | 32.2 |
| 14 | 61 | 34.2 |
| 15 | 59 | 35.4 |
| 16 | 58 | 37.1 |
| 17 | 57 | 38.8 |
| 18 | 56 | 40.3 |
| 19 | 55 | 41.8 |
| 20 | 54 | 43.2 |
| 21 | 53 | 44.5 |
| 22 | 53 | 46.6 |
| 23 | 52 | 47.8 |
| 24 | 51 | 49.0 |
| 25 | 51 | 51.0 |
| 26 | 50 | 52.0 |
| 27 | 50 | 54.0 |
| 28 | 50 | 56.0 |
| 29 | 49 | 56.8 |
| 30 | 49 | 58.8 |
| 31 | 49 | 60.8 |
| 32 | 48 | 61.4 |
| 33 | 48 | 63.4 |
| 34 | 48 | 65.3 |
| 35 | 47 | 65.8 |
| 36 | 47 | 67.7 |
| 37 | 47 | 69.6 |
| 38 | 47 | 71.4 |
| 39 | 47 | 73.3 |
| 40 | 46 | 73.6 |