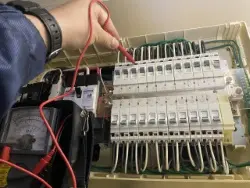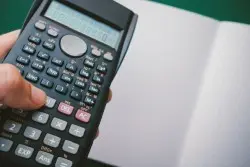ダイオキシン
ダイオキシンは、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)という3種類の有機塩素化合物の総称である。これらは意図的に生産されることは稀で、主に人間活動や自然界での燃焼プロセスにおいて、副生成物として発生する。
ダイオキシンはその構造に塩素を含む物質が燃焼する際に生成されやすい。主な発生源はごみ焼却炉、アルミニウム合金製造時の溶解炉、化学物質の製造工程などであるが、火山の噴火や森林火災といった自然現象でも微量ながら生成されることがある。
物理的・化学的性質として、非常に安定しており分解されにくい(難分解性)という特徴を持つ。また、水に溶けにくく、脂肪に溶けやすい性質があるため、環境中に放出されると土壌や水底の底質に長期間残留し、食物連鎖を通じて魚介類や肉、乳製品などの脂肪分の多い食品に蓄積されるおそれがある。人の体内に入った場合も、脂肪組織に蓄積され、半減期は約7年と非常に長いため長期に渡って悪影響を及ぼす。
人体への影響と安全性の評価
ダイオキシン類は毒性が強く、特に2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシン(TCDD)は極めて強い毒性を持つことが知られている。
動物実験では、高濃度で曝露された場合に発がん性、生殖毒性、免疫毒性、甲状腺機能への影響などが報告されている。人に対する影響については、過去の事故による高濃度曝露の知見から発がん性が認められているものの、現在の日本の一般的な環境汚染レベルにおいて、直ちに健康影響が生じることはないと考えられている。
安全性の指標として「耐容一日摂取量(TDI)」が設定されている。これは生涯にわたって毎日摂取し続けても健康影響がないとされる量であり、日本では現在4pg-TEQ/kg体重/日とされている。日本人が通常の生活で食事などから摂取しているダイオキシン類の平均的な摂取量は、このTDIを下回る水準であり、健康に影響を与えるものではないと評価されている。
ダイオキシン対策と現状
ダイオキシン問題に対応するため、日本では「ダイオキシン類対策特別措置法」(ダイオキシン法)が2000年1月に施行された。この法律に基づき、排出基準の設定、環境基準(大気、水質、土壌)の設定、排出量の削減計画などが進められている。
- ごみ焼却炉の構造や維持管理に関する基準の厳格化
- 低温での焼却を避けるなどの燃焼プロセス管理
- ごみの減量化や適正処理の推進による発生抑制
これらの取り組みの結果、日本の事業活動に伴うダイオキシン類の排出総量は、規制法律の施行以降に大幅削減されてきた。環境中のダイオキシン類濃度もほとんどの地点で環境基準を達成しており、汚染状況は改善傾向にある。
国際的にも、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約などにより、ダイオキシン類を含む有害物質の削減に向けた世界的な取り組みが進められている。今後も、国民の健康と環境を守るため、継続的な監視と対策の推進が重要であるとされている。