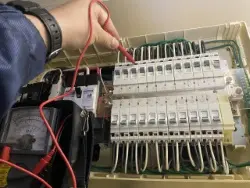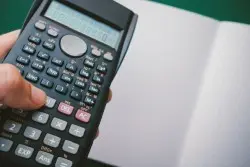酸性雨
酸性雨とは、工場や自動車から排出される大気汚染物質が原因で、通常よりも強い酸性を示す雨、雪、霧などの降水のことである。本来、大気中の二酸化炭素が溶け込むことによって、雨はわずかに酸性(pH約5.6)を示すが、酸性雨はそれよりもpHが低い(酸性が強い)状態で、pH5.6以下の降水を指すことが多い。
原因物質は人為的
酸性雨の主な原因物質は、硫黄酸化物(SOx)と窒素酸化物(NOx)である。これらは、石炭や石油などの化石燃料を燃焼させる際に発生する。火力発電所や製鉄所などの大規模工場、そして自動車の排気ガスが主要な発生源となるとされる。
これらのガスが大気中に放出されると、紫外線やオゾンなどの作用により酸化され、最終的に硫酸や硝酸といった強い酸性の物質に変化する。この酸性物質が雨や雪、霧などに溶け込み、地上に降り注ぎ酸性雨となる。また、これら酸性物質は風に乗って長距離を移動するため、発生源から遠く離れた地域や他国にまで被害を及ぼすという、広域的・国際的な側面を持つ点も大きな特徴である。
環境・インフラへの深刻な影響
酸性雨は、地球環境や人々の暮らしにさまざまな深刻な影響をもたらす。下記にいくつか事例を紹介する。
生態系への影響
湖沼や河川に降り注ぐことで水質が酸性化し、魚類や水生昆虫、プランクトンなどが死滅することがある。北欧や北米では、かつて「死の湖」と呼ばれる、生物が全く住めなくなった湖が多数発生した。土壌が酸性化すると、樹木が養分を効率よく吸収できなくなったり、アルミニウムなどの有害な重金属が溶け出して根を傷つけたりする。これにより、森林の生育が阻害され、広範囲にわたる立ち枯れ被害を引き起こす。ドイツの「シュヴァルツヴァルト(黒い森)」の被害は特に有名である。
建造物・文化財への影響
大理石や石灰岩でできた歴史的建造物や銅像は、酸によって表面が侵食され、外観が損なわれたり風化が早まったりする。ギリシャのパルテノン神殿なども被害を受けており、鉄筋コンクリートの劣化を早め、橋梁やその他のインフラ設備の寿命を縮める要因にもなる。
人体への影響
酸性雨を直接人体に浴びることによる健康被害は少ないとされているが、酸性度の高い「酸性霧」を吸い込むことによる呼吸器系への影響が懸念されている。土壌から溶け出した有害物質が食物連鎖を通じて間接的に人体に取り込まれる可能性も指摘されている。
国際的な取り組みと今後の課題
酸性雨による被害を受け、世界各国では酸性雨問題に対し、国際的な枠組みでの対策が進められている。「長距離越境大気汚染条約(CLRTAP)」や国内法による排出規制、脱硫・脱硝装置といった高度な排ガス処理技術の導入などにより、先進国を中心に原因物質の排出量は減少傾向にある。
現在も東アジアをはじめとする一部の地域では、経済発展に伴うエネルギー消費量の増加により、酸性雨問題は依然として重要な環境課題である。この問題の解決には、技術的な対策に加えて、日々の生活における行動の見直しも不可欠である。省エネルギーの意識や公共交通機関の利用促進など、小さな取り組みの積み重ねが、大気汚染物質の抑制につながるとされている。