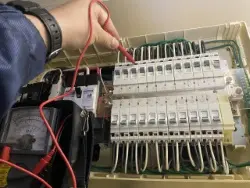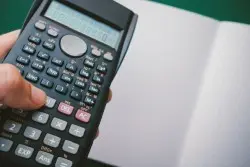異種間金属接触腐食
異種の金属が接触していると、卑金属側(アノード:低電位側)の腐食が促進され、貴金属側(カソード:高電位側)の腐食が抑制される現象のこと。ガルバニック・コロージョンとも呼ばれる。
金属体は水分や塩分によって酸化が促進し腐食することがあるが、異種の金属体同士が接触すると電位差によって電流が流れ、陽極となる部分に電流が集中することで腐食が進行する。
異種金属の接触により腐食が発生するおそれがある場合、腐食防止のためゴムシートなどのスペーサで離隔を確保したり、コーティングにより金属体同士の絶縁を図るといった手法が採用される。
面積比による腐食防止
「電位が大きく異なる金属同士を接触させない」というのは効果的な防食手法であるが、全ての金属同士を接触させない施工は難しい。ゴムなどの絶縁体を金属間に挟み込むのは効果的な防食だが、コストや施工労務の増加、施工難度による観点から難しい場合、面積比を大きく確保する防食法がある。
大きな卑金属体に対して、接触する貴金属体の面積が十分小さければ、腐食するおそれが軽減される。ここで、ステンレスと鉄を例として解説する。
ステンレス合金は貴金属側であり、銅に近い標準電極電位を持っているとされる。卑金属である鋼板に対し、小さなステンレスボルトを用いて固定しても早期腐食にはつながらない。
ステンレスシンクに鉄釘やネジを乗せるとすぐに腐食することからわかるように、面積の大きな貴金属体に卑金属を接触させてはならない。ステンレスの母材に対してアルミリベット等を接触させる施工をすると、早期にリベットが腐食してしまう。

亜鉛めっきによる防食
鉄と亜鉛を例とした事例を紹介する。鉄は亜鉛よりも基準電位が高いため、接触状態になると亜鉛側の腐食が進行するが、鉄側の腐食が制限される。配管や屋根材料などは亜鉛めっきの製品が多いが、亜鉛めっきにより、配管や屋根の主材料である鉄鋼の腐食を制限できる。
これは、意図的に異種金属を接触させることで、片方の金属体を保護する「犠牲防食」という手法である。前述した亜鉛めっきが代表例であり、鉄鋼に亜鉛めっきを施すことで、引っかき傷やピンホールが発生しても、亜鉛めっき部分が鉄鋼部分に代わって腐食し、鉄鋼部分を保護する。
埋設オイルタンクを接地する場合、鉄に対して直接銅板を接続すると、銅板が保護され、オイルタンク側の腐食が進行し易くなる。埋設オイルタンクを接地する場合、電気伝導率は低くなるが、溶融亜鉛めっき鋼板を用いるのが良い。
導体として用いられる金属の標準電極電位
| 名称 | 標準電極電位V |
|---|---|
| 銀 | +0.799 |
| 銅 | +0.340 |
| スズ | -0.138 |
| ニッケル | -0.257 |
| 鉄 | -0.440 |
| 亜鉛 | -0.763 |
| アルミニウム | -1.676 |
塩害を原因とした腐食に関する情報については塩害地域と塩害対策・海岸からの距離を参照。