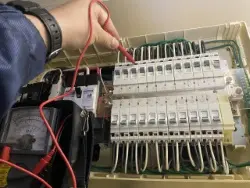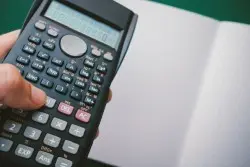分流器
直流電流計の測定範囲の拡大に使用する抵抗器で、電流計に並列に接続し、電流計に流れる電流を分流させて測定範囲を拡大する。電流の性質として、抵抗値が低い経路ほど多くの電流が流れるという法則を利用している。
電流計は通常、測定できる電流の最大値(定格電流)が決まっている。定格を超える電流を直接流すと、計器が破損してしまう。そこで、分流器を並列に接続することで、測定したい大きな電流の大部分を分流器側にバイパスさせ、電流計には許容範囲内の小さな電流だけを流すようにする。これにより、電流計の測定範囲を広げることが可能となる。
回路全体の電流は、電流計に流れた電流と分流器に流れた電流の合計である。分流器の抵抗値と電流計の内部抵抗値の比率(分流比)を知ることで、電流計の指示値から全体の電流値を正確に計算できる。
精密な測定が求められるため、温度変化による抵抗値の変化が少ないマンガニンやニクロムといった特殊合金が使用されることが多い。電力損失(ジュール熱)を効率よく放熱できるよう、大型のものは金属板を折り曲げた形状や、フィン付きの構造になっている場合がある。小型のものはチップ抵抗型も存在する。計測用であるため、抵抗値の許容誤差は非常に厳密に管理されており、0.1%や0.5%といった高精度の製品が一般的である。
分流器の主用途
既存の電流計で、より大きな電流を測定するために使用される。例えば、1Aまでしか測定できない電流計で10Aを測定する場合、電流計に流れる電流が全体の1/10になるような抵抗値の分流器を接続する。
分流器は回路内の電流値を間接的に測定するためにも使用される。分流器は精密な抵抗値を持っており、その両端に発生する電圧降下(オームの法則 V = I × R に基づく)を電圧計で測定することで、流れている電流Iを算出する。この用途に用いる場合は「シャント抵抗器」と呼ばれることが多い。モーター制御やバッテリー管理など、多くの電気機器で重要な役割を果たしている。
分流器の選定
可動コイル形計器で計測できる電流値は制限があるため、大電流を測定する場合には分流器の使用が必須となる。メーカー標準品として、7.5A程度の小電流から、6kAを超えるような大電流までを計測可能範囲まで分流し、入力範囲を拡大可能となる。
分流器に流す電流は定格電流の80%を上限とし、定格電流の1.5倍以上の裕度があるよう選定するのが良い。定格電流に近い電流を長時間流すと、機器発熱による焼損や誤差の原因となるため避ける。端子電圧は60mV、100mVが標準である。
分流器は、計器に内蔵される場合と外付け設置する場合があり、外付け分流器を使用する場合は抵抗値の誤差が発生するため注意が必要。「接続線の電圧降下」「温度変化による抵抗値の変動」「端子接触抵抗」など、外部要素が誤差の発生要因になることに注意を要する。