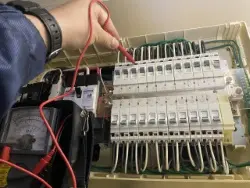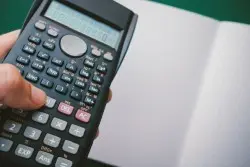電気工事施工管理の概要
施工管理技術検定は、高度化・専門化・多様化が進む建設工事の施工に際し、建築技術の向上を目指す目的で実施される試験である。主に建築工事を掌握する「建築施工管理」、給排水衛生・空調工事を掌握する「管工事施工管理」、電気工事を掌握する「電気工事施工管理」などがある。
電気工事施工管理とは「施工計画・施工図の作成」「工程管理」「品質管理」「安全管理」など、施工管理を的確に行うために必要な技術を規定している。
電気工事施工管理を的確に行うためには電気工学の基礎知識・施工管理法・電気法規を習得することが不可欠であり、この資格を受験し資格取得ができれば、高い技術力を持っているとして国から認定を受けられる。
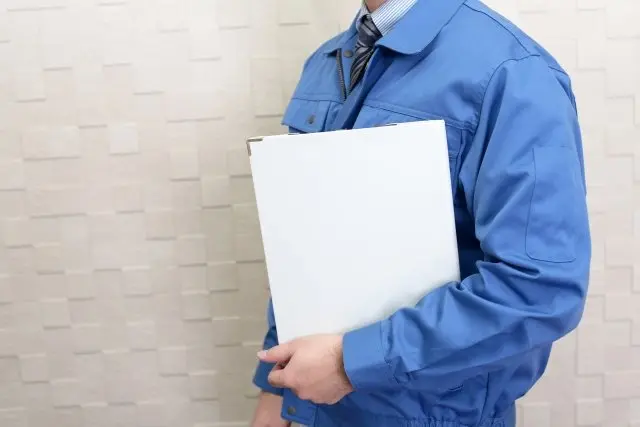
施工管理技士資格取得で行える業務範囲
施工管理技士資格を取得すれば、一般建設業や特定建設業における営業所に置く専任技術者や、建設費工事現場に置く主任技術者や監理技術者として認められる。建設業の経営事項審査の技術力評点にカウントされるなど、数多くのメリットがある。
電気工事は指定建設業に含まれるので「電気工事の営業所ごとに置かなければならない専任の技術者」と「建設工事の現場ごとに置かなければならない監理技術者」として、電気工事施工管理技士の資格が活用できる。
電気工事施工管理技士資格を取得しても、電気工事の作業に従事できるわけではない。電気主任技術者の資格も同様、電気工事の作業に従事するためには、従事する作業に応じた「電気工事士」の資格を取得しなければならない。
2級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士は、一般建設業の営業所における専任技術者・主任技術者として業務できる国家資格である。特定建設業の電気工事の主任技術者または監理技術者になることはできない。
一般建設業では、発注者から直接請け負う金額が、電気工事1件につき4,500万円を超えない金額の下請契約を結ぶことができる。4,500万円以上の下請契約を結ぶ場合、特定建設業の許可が必要となる。
発注者から4,500万円を超える大規模工事を請け負った場合でも、自社で直接施工することで下請契約の総額を4,500万円未満に抑えられるなら、一般建設業の許可でも問題ないとされている。
受験資格と実務経験
令和6年の法改正により、2級電気工事施工管理技士の受験資格について大きく変更されており、下記表の区分に該当する者が二次検定を受験できることとされた。
| 受検区分 | 前提となる検定等 | 実務経験年数 | |
| 1 | 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定合格 | 合格後3年以上 | |
| 2 | 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定合格 | 合格後1年以上 | |
| 3 | 電気工事士試験または電気主任技術者試験の合格または免状交付ならびに、1級電気工事施工管理技術検定第一次検定または1級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格 | 電気工事士または電気主任技術者の試験合格または免状交付後1年以上 | |
一次検定は満17歳以上であれば受験可能であり、特段の実務経験は求められていない。下記に、旧制度における必要な実務経験を示す。括弧内は指定学科以外の必要実務経験である。
- 大学・専門学校の高度専門士:卒業後1年以上(1年6ヶ月以上)
- 短期大学・高専・専門学校の専門士:卒業後2年以上(3年以上)
- 高校:卒業後3年以上(4年6ヶ月以上)
- その他:8年以上
電気主任技術者資格または第二種電気工事士であれば、1年以上の実務経験年数で受験が可能である。なお、第一種電気工事士は既に一定の電気工事に関する実務経験を積んでいると認定されるため、新たな実務経験は不要である。
2級電気工事施工管理技士の難易度・合格率
一次試験として学科試験が行われ、二次試験は自身の電気工事施工経験に基づく記述試験となる。一次試験の合格率は、50%~60%、2次試験は40~50%程度とされており、全体では25%程度の合格率となる。一次試験は全体の60%程度の正答率で合格するとされているが、二次試験の合格基準は発表されていない。
一次試験の難易度は、第一種電気工事士や、第三種電気主任技術者の資格と比べ簡単である。電気工学分野としてオームの法則、キルヒホッフの法則を用いた基礎的電気回路の計算、コンデンサやコイルに蓄えられる電荷、発電機・電動機の基礎などが出題されるが、求められる知識は広く浅いものである。
試験問題
試験科目は、電気工学・電気設備・関連分野・施工計画・法規の5つに分けられ、それぞれの分野で回答する問題を選択する。各々の分野毎、得意とする問題を選択して回答できるため、受験者の得意分野に応じた試験対策できる。
二次試験は「経験した工事に関する工事名」「施工場所と工事の内容」「安全面・工程面などから留意した事項」「その対策」記載する問題や、指定された電気工事に関する用語について解説する問題が出題される。
技術的内容とは「施工上の留意点、選定上の注意点、対策、方式、方法、用途、目的、特徴、動作原理、発生原理、定義」と定められており、指示された内容に応じて、上記内容を詳細に記載する。与えられた空欄に80%以上を埋めておけば安心である。
電気工事に関する技術的内容を記載することが大原則であり、建設工事に係るものなど、電気工事以外の技術的内容を記載すると減点対象となる。誤字脱字が多い、文字が読めないといった点も勘案されるため、丁寧な記載が求められる。
1級電気工事施工管理技士
1級電気工事施工管理技士は、特定建設業の営業所における専任技術者・主任技術者・監理技術者になれる国家資格である。2級電気工事施工管理技士の上位資格に位置付けられるため、一般建設業の専任技術者・主任技術者になることも可能である。
特定建設業では、発注者から直接請け負う金額が、電気工事1件につき4,500万円以上の下請契約を結ぶことが可能となる。
受験資格と実務経験
令和6年の法改正により、1級電気工事施工管理技士の受験資格についても大きく変更されており、下記表の区分に該当する者が二次検定を受験できることとされた。一次検定は満19歳以上であれば受験可能であり、特段の実務経験は求められていない。
| 区分1 | 1級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格者 | |
| 1-1 | 「1級電気工事施工管理技術検定第一次検定」合格後、実務経験5年以上 | 二次のみ |
| 1-2 | 「1級電気工事施工管理技術検定第一次検定」合格後、特定実務経験( ※1)1年以上を含む実務経験3年以上 | 二次のみ |
| 1-3 | 「1級電気工事施工管理技術検定第一次検定」合格後、監理技術者補佐( ※2) として実務経験1年以上 | 二次のみ |
| 区分2 | 2級電気工事施工管理技術検定第二次検定合格者で、かつ、1級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格者 | |
| 2-1 | 「2級電気工事施工管理技術検定第二次検定」合格後実務経験5年以上 | 二次のみ |
| 2-2 | 「2級電気工事施工管理技術検定第二次検定」合格後、特定実務経験( ※1)1年以上を含む実務経験3年以上 | 二次のみ |
| 区分3 | 2級電気工事施工管理技術検定第二次検定合格者で、かつ、1級電気工事施工管理技術検定第一次検定受検予定者 | |
| 3-1 | 「2級電気工事施工管理技術検定第二次検定」合格後実務経験5年以上 | 一次・二次 |
| 3-2 | 「2級電気工事施工管理技術検定第二次検定」合格後、特定実務経験( ※1)1年以上を含む実務経験3年以上 | 一次・二次 |
| 区分4 | 第一種電気工事士試験合格者で、かつ、1級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格者 | |
| 4-1 | 「第一種電気工事士試験」合格後、実務経験5年以上 | 二次のみ |
| 4-2 | 「第一種電気工事士試験」合格後、特定実務経験( ※1)1年以上を含む実務経験3年以上 | 二次のみ |
| 区分5 | 第一種電気工事士試験合格者で、かつ、1級電気工事施工管理技術検定第一次検定受検予定者 | |
| 5-1 | 「第一種電気工事士試験」合格後、実務経験5年以上 | 一次・二次 |
| 5-2 | 「第一種電気工事士試験」合格後、特定実務経験( ※1)1年以上を含む実務経験3年以上 | 一次・二次 |
一次検定合格者は「1級電気工事施工管理技士補」となり、監理技術者の補佐として監理技術者の指導監督を受けながら、現場の主任技術者としての業務が遂行できる。
令和10年までの措置として、下記のような「制度改正前の旧受験資格」による受験が可能となっている。なお、いずれも1年以上の「指導監督的実務経験」を含むことが必要とされている。
- 大学・専門学校の高度専門士:卒業後3年以上(4年6ヶ月以上)
- 短期大学・高専・専門学校の専門士:卒業後5年以上(7年6ヶ月以上)
- 高校:卒業後10年以上(11年6ヶ月以上)
- その他:15年以上
実務経験とは
工事の実施にあたって、施工計画の作成、当該工事の工程管理、品質管理、安全管理など、工事の施工管理に直接的に関わる技術上の職務経験を指すものである。これは工事監理補助者であっても良い。基本的には「施工管理」「施工監督」「設計監理」の3業務が実務経験としてカウントされる。
施工管理は、工事請負者の従業員として請負工事の施工を管理した経験を実務経験としてみなしている。派遣により従事した場合でも支障ない。
施工監督は、工事発注者の従業員として発注工事の施工を指導・監督した経験を実務経験としてみなしている。ディベロッパーの品質管理担当など、発注者所属の技術者も実務経験として差し支えない。
設計監理は、工事監理業務等受託者の従業員として、対象工事の工事監理を行った経験を実務経験としてみなしている。設計及び監理業務の一括受注の場合、工事監理業務期間のみが該当するため、基本設計や実施設計といった業務は実務経験としてカウントできない。
特定実務経験とは
建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円以上の電気工事、建築一式工事では7,000万円以上の工事において、監理技術者資格者証を持つ監理技術者または主任技術者の指導の下、電気工事施工管理の実務経験を得た場合、特定実務経験として扱われ、比較的短い期間の実務経験で受験が可能となる。
これは自らが監理技術者若しくは主任技術者として行った電気工事施工管理の実務経験も同様、特定実務経験として扱われる。ただし、発注者側の品質管理者や、監理業務受託者としての業務の場合、監理技術者の指導の下での業務として扱われないため、特定実務経験としては扱われない。
1級電気工事施工管理技士の難易度・合格率
2級電気工事施工管理技士と同様、一次試験として学科試験が行われ、二次試験は自身の電気工事施工経験に基づく記述試験となる。一次試験の範囲が拡充され、午前・午後に分けて試験が実施される。
一次試験の合格率は、30%~40%、2次試験は60~70%程度とされており、全体では25%程度の合格率となる。試験の難易度は第一種電気工事士に近くなり、高度で専門的な問題が出題される。
資格取得による免除規定
1級電気工事施工管理技士の資格取得者は、民間資格「計装士」の「学科B」について免除を受けられる。民間資格ではあるが、国土交通省管轄である建設業法に定められた「経営事項審査加点対象」の加点対象となっており、多くの電気工事会社で取得が奨励されている。
建築物の電気設備工事で一般に「計装」という場合、空調や給排水などを自動制御する「ビルディングオートメーション」のシステム構築である。
各種リレーや電磁弁、センサーなどを駆使し、流体の供給量や圧力を制御したり、セントラル空調の冷温水温度やダクト風量などを制御する「自動制御設備」に関連する資格であるが、計装に関わる専門技術だけでなく、施工管理や安全衛生についても資格試験で問われる。
計装士試験の「学科B」は、配管配線工事の「施工管理」、労働安全衛生法の「安全衛生」「法規」の試験問題であり、施工管理技士資格の取得者はすでに十分な知識があるものと見なされ、学科試験の免除が受けられる。
試験問題の事例
試験問題の基本的内容は2級電気工事施工管理技士と同様で、一次試験は電気工学や施工管理、法規について問われる出題である。試験難易度は2級よりも高くなるが、基本的事項に留まるため過去問題を重点的に学ぶことで合格可能である。
二次試験も同様に、電気工事に関する経験などを記載する内容であり、指南書を使用して事前に記載内容を準備するのが重要である。試験対策としてまとめた項目を紹介する。なお、受験者が施工管理において体験した内容によりアレンジが必要である。
なお下記の事例は令和6年の改正前から作成したものであるが、工事現場における管理業務として大きな食い違いがないことから、そのまま継続掲載としている。
経験した工事の基本情報
- 工事名:
- 工事場所:
- 請負金額:
- 概要:
- 工期:平成 年 月 日~平成 年 月 日
- 立場:設計監理
- 担当業務:電気設備工事の設計監理
工程管理上留意したこと(2項目)
- 事項:受電時期を遅らせないよう留意した
- 理由:受電後に後続工事が開始となり、受電の遅れがクリティカルパスに影響するため
- 措置①:キュービクル用基礎の先行構築を指示した
- 措置②:納入仕様書の早期確認を行い、発注者承認の手続きを迅速に進めた
- 結果:対策により、マスター工程に遅延することはなかった
- 事項:防災センター・電気室・EPS の構築時期に留意した
- 理由:長期に渡る試運転調整が必要となる、各種制御装置の中枢となるため
- 措置①:EPS 間仕切りの先行構築を指示した
- 措置②:防災センター区画の先行構築を指示した
- 結果:対策により、マスター工程に遅延することはなかった
工程管理に関する問題点と改善策(2項目)
- 問題点:幹線分岐が多い計画において、ケーブルの現地接続が多く、労務の増大による工程の遅れが懸念された
- 対策:幹線の現地分岐を行わずプレハブユニットケーブル工法を採用し、労務の低減を図り工程短縮に寄与した
- 問題点:悪天候による風雨の吹き込みにより、電気室・EPS に水が浸入し、電気機器の絶縁不良が発生するおそれが懸念された
- 対策:先行して屋根・壁の構築を指示し、電気関連室の雨仕舞を完了させ、天候に影響のない工事が可能となった
労働災害防止上、留意したこと(2項目)
- 事項:キュービクル受変電設備の搬入据付に伴う他作業への危害に留意した
- 理由:キュービクル受変電設備の設置スペースまでに、他作業動線との交錯が著しい
- 措置①:機器搬入の施工要領書を作成させ、安全に作業可能かを確認した
- 措置②:交錯が予測される場所への監視人の配置を指示した
- 結果:対策により、災害発生無く作業完了した
- 事項:高所への照明器具取付における落下事故に留意した
- 理由:高さ2m を超える場所への器具取付数が多いため
- 措置①:脚立作業ではなく、足場構築による作業を指示した
- 措置②:作業に必要な適正照度の確保を指示した
- 結果:対策により、災害発生無く作業完了した
労働災害発生に関する問題点と改善策
- 問題点:受変電設備の設置工事において、多数の作業員が交錯することによる安全上の懸念があった
- 対策:施工要領書・作業手順書を作成させ、指揮系統と作業手順を明確化し、予定外作業が発生しないよう務めた
- 問題点:改修工事において電動工具を施設既存コンセントから使用していたが、漏電時の保護に懸念があった
- 措置①:既存のコンセントを利用する場合は、既存コンセントに高速型漏電遮断器付きのコンセントを差し込み、漏電保護を行った上で使用するよう指示した
- 結果:対策により、災害発生無く作業完了した
品質確保における重要項目
材料・機器
- メーカーカタログにて製造者・製造年月日・工場試験データ等を確認する
- 保管場所における、耐候性・耐熱性に問題がないかを確認する
- 現場搬入されたものに損傷や異常がないか確認する
機器取付
- 取付場所の検討、取付詳細図を作成する
- 機器の搬出入・機器扉の開閉・メンテナンススペースを確認する
- 設置場所における、耐候性・耐熱性に問題がないかを確認する
配管施工・ケーブル施工
- 設計図書に記載されている施工方法を確認する
- 作業者の電気工事士免状の取得状況を確認する
- 施工場所における、耐候性・耐熱性に問題がないか確認する
防錆
- スチール材料には錆止塗装を行うことで発錆を防止する
- アルミニウム材料は酸やアルカリに侵食されないような場所で使用する
- ステンレス材料はSUS304、SUS316 など性能が大きく違うため選定に留意する
防音
- 騒音を嫌う部屋から離隔する
- 周囲を囲って発生音を遮断する
- 支持固定は防振ゴムなどを介し、躯体伝播音を防止する
防振
- 据付部にコンクリート基礎を設け、振動を減衰させる
- 据付部に防振ゴムを設けて振動を吸収する
- 配管にフレキシブル継手を用いて振動伝搬を防止する
耐震
- 電気機器は移動・転倒しないよう建築躯体に強固に固定する
- 電気機器は床置きを基本とし、天吊や壁掛けを避ける
- 据付面積に対して高さが高い機器は、頂部・背面から振れ止めを施す
防水
- 機器に水が侵入しないよう機器と躯体の間にシールを打つ
- 換気口に雨返しを設ける
- 屋外につながる配管は水勾配を屋外に向ける
塩害
- 塩害対策塗装を行い、定期的な塗り直しを行う
- 汚損時の洗浄を行う
- 換気口に除塩フィルタを設ける